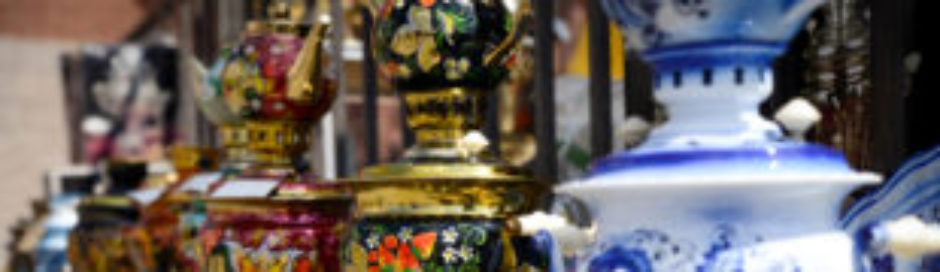前回に続き、パソバ・オリガさんの学位論文を取り上げます。タイトルは「日本におけるロシア語話者「移民」の子どもへの継承ロシア語教育の展望 : バイリンガル教育からの視点」で、その中の先行研究についてまとめられた部分を以下要約します。
言語発達の著作においては、継承語教育に関して中島和子(1998(a);1998 (b);2000 ;2005;2006; 2010;2012)の研究が数多くあげられる。また、学校や環境における2 言語習得についてカミンズ(1980; 2007;2011)の研究蓄積が大きい。
カミンズは、習得時間の差に注目して言語能力の内部構造をBICS とCALP の2 つに分けた。BICS はBasic Interpersonal Communicative Skills(会話力)で、対人関係における基礎的なコミュニケーション能力を指しに用いられる。CALP はCognitive Academic Language Proficiency(学習言語)で、これは、推測・比較する認知的なツール、教科内容と教科用語、教科別教室談話、学習ストラテジーなど全体を含めるものである。しかし、この2 件は、誤解が多くなされ、批判された。例えば、中島・ヌナス(2001)は、異言語間で学齢期を過ごす児童の会話におけるCALP 面の習得の必要性を重視しており、「CALPという概念は必ずしも語彙、読解力に限られたものではないが、会話力におけるCALP面はほとんど言及されることなく、BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills)というレッテルをはられ」る傾向があると指摘している。
カミンズ・中島(2011)は、CALPとBICS という二つの側面を以下のようにCF とDLS とALP を三つに広げて、子どもの言語発達を見ようとしている。
1) 会話の流暢度(Conversational Fluency,CF またはBICS)は、頻度の高い語彙と簡単な文法を含み、外国人児童・生徒は、1、2 年で習得ができる。
2)弁別的言語能力(Discrete Language Skills, DLS)従来はCALP の中に込み込まれていた基礎的な文法や文字の習得が含まれるが、5~7 年もかかるCALP とは異なり外国人児童・生徒も母語話者(母語児童)とほぼ同じ、1、2 年で習得するものである。
3)教科学習言語能力(Academic Language Proficiency, ALP または 従来のCALP)は読字力、作文力、抽象語彙などが含まれ、複雑な話し言葉と書き言葉を理解し、産出する力と低頻度の語彙と複雑な文型、教科学習では言語的にも概念的にも高度な文章の理解頻度の高い語彙と簡単な文法構造にさらに分類され、それぞれを身につけるまでの時間が異なり、前者は5 年以上を必要とするのに対し、後者は5 年~10 年程度を要する。一番大事なAcademic Language Proficiency は9 歳から10 歳頃から急速に伸びると言われている。これが学習に必要な能力で、日本語なら漢字語彙も含まれている。カミンズ・中島 (2011)はALP を定義して「学校という文脈で効果的に機能するために必要な一般的的な教育知識とメタ認知ストラテジーを伴った言語知識」[カミンズ・中島 2011:Ibid.]という。特にリテラシーとの関わり(読書の量と幅、読みストラテジー、読書に対する態度と姿勢と読書習慣、そして多読、多書)が強調されている。
CALPと BICSについては言語を生業としている人にとっては理解が必須の概念ですが、それをさらに進化させたのがカミンズ先生と中島先生の上記の理論です。特にALPが9、10歳で急速に伸びるのは、子供の教育においてのJarucoでの経験則とよく合致します。
またメタ認知ストラテジーも言語教育によく用いられる用語ですので、まずは言語学習におけるストラテジーを包括的に紹介しておきます。言語学者のOxfordが1990年に以下のようにまとめました。
直接ストラテジー
1.記憶ストラテジー(Memory Strategies)
a.知的連鎖を作る:①グループに分ける ②連想をする/十分に練る ③文脈の中に新しい
語を入れる
b.イメージや音を結びつける: ①イメージを使う ②意味地図を作る ③キーワードを使う
④記憶した音を表現する
c.繰り返し復習する: ①体系的に練習をする
d.動作に移す: ①身体的な反応や感覚を使う ②機械的な手段を使う
2.認知ストラテジー(Cognitive Strategies)
a.練習をする: ①繰り返す ②音と文字システムをきちんと練習する ③決まった言い回し
や文型を覚えて使う
b.情報内容を受け取ったり,送ったりする:①意図を素早くつかむ ②情報内容を受け
取ったり,送ったりするために様々な資料を使う
c.分析したり,推論したりする:①演繹的に推論する ②表現を分析する ③(言語を)対
照しながら分析する ④訳す ⑤転移をする
d.インプットとアウトプットのための構造を作る: ①ノートを取る ②要約をする ③強調
をする
3.補償ストラテジー(Compensation Strategies)
a.知的に推測する: ①言葉的手掛かりを使う ②非言語的手掛かりを使う
b.話すことと書くことの限界を克服する: ① 母語に変換する ②助けを求める ③身ぶり
手ぶりを使う ④コミュニケーションを部分的に,あるいは,全く避ける ⑤話題を選
択する ⑥情報内容を調整したり,とらえたりする ⑦新語を造る ⑧婉曲的な表現や類
義語を使う
間接ストラテジー
4.メタ認知ストラテジー(Metacognitive Strategies)
a.自分の学習を正しく位置づける: ①学習全体を見て,既知の材料と結び付ける ②注目
する ③話すのを遅らせ,聞くことに集中する
b.自分の学習を順序立て,計画する:①言語学習について調べる ②組織化する ③目標と
目的を設定する ④言語学習タスクの目的を明確にする(目的をもって聞く,読む,話
す,聞く)⑤言語学習タスクのために計画を立てる ⑥実践の機会を求める
c.自分の学習をきちんと評価する:①自己モニターする ②自己評価する
5.情意的ストラテジー(Affective Strategies)
a.自分の不安を軽くする: ①斬新的リラックス法,呼吸法,黙想を活用する ②音楽を使
う ③笑いを使う
b.自分を勇気づける:①自分を鼓舞する言葉を言う ②適度に冒険をする ③自分を褒める
c.自分の感情をきちんと把握する:①体の調子を診る ②チェック・リストを使う ③言語
学習日記をつける ④他の人々と自分の感情について話し合う
6.社会的ストラテジー(Social Strategies)
a.質問をする: ①明確化,あるいは確認を求める ②訂正してもらう
b.他の人々と協力する: ①学習者同士協力する ②外国語に堪能な人と協力する
c.他の人々への感情移入をする: ①文化を理解する力を高める ②他の人々の考え方や感
情を知る
以上ストラテジー分類
最後にオリガさんの学位論文の中に、言語教育での読書の重要性が述べられています。これは経験則でもよく理解できることですが、研究結果から読書量、読書への意欲・態度の効果が示されており、Jarucoでも確信を持って、読書への意欲を掻き立てることを教育方針のひとつとしています。