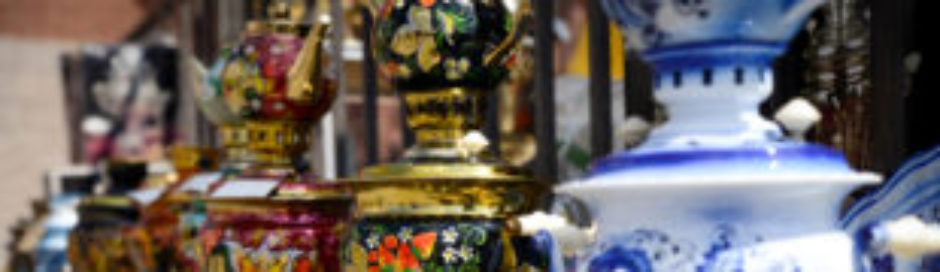前回に引き続き、パソバさんの学位論文から、日本における今後のロシア語教育に関する提言が書かれた部分を紹介いたします。
親による学校の選択、教員による教科書や、指導方法の選択は、親の動機づけ、学力に対する期待やビリーフによって、どの程度会話とリテラシーが伸ばせるか、どの程度読み書きが伸ばせるのか、リテラシーとの関わりを強めるのか、指導する上での目的によって手法が異なる。また、カミンズ・中島(2011)による、教科書の選択についての指摘は、きわめて重要である:「学校の中で社会の主要言語で書かれた教科書を基盤とした
単線のリテラシーのみに焦点を当てるのは、極めて限界のある指導方針であ」るという。カミンズ・中島(2011)は、日本の学校におかれた児童・生徒に対して述べているが、筆者は、それと同様に、ロシア全国で使用される「ロシア語母語話者」を対象にした教科書が、限られた言語使用状況にある「ロシア語継承語話者」に使用されている「付属学校」、特に2.5 世のことを考えると、同様に限界のあると認めざるを得ない。
ロシア語が開設された学校においてロシア語を履修したい日本人が減っている一方、今後は、ロシア語継承語話者(ルソフォーン(74))の編入が予測される。それによって、大学や高校の状況が肯定的に転向すると思われる。まずは、学習動機の働きで、ロシア語の社会的なステータスが上がると思われる。この意味で、イ・ヨンスク(2009)が指摘している通り、「多言語」の「多」そのものの肯定である限り、近代国家が目指してきた「単一言語主義」に対するアンチテーゼであり、思想史的に言えば、「近代」を乗り越えようとする一つの試みである。多言語主義(plurilingualism)については、林田(2010:134)の以下の提示がある:「複言主義、生涯教育という2 本の柱を中心にした、(74) フランコフォーンに類似じた用語である[Kудрявцева 2008]。家庭に限られているロシア語によるコ
ミュニケーションの継承語話者である。
多言語・多文化教育の一環としての中等・高等一貫のロシア語教育体制というものを視野に入れ、高校、大学教員のみならず、都道府県教育委員会や学会を含めた連帯ネット・ワークを作り、①教育・学習プログラムの作成、②教材、指導方法の研究・開発とその普及、③教員養成、④教員配置 の各点について早急に検討・作業を進めていくことが求められている」。しかし、カリキュラムには、新たに継承語話者の枠を別に設けないと、今までの第二外国語としての指導手法では適切であるといい難い。それに関連して、HLL (heritage language learners) の特徴についてMasako O. Douglas (2008) の指摘をあげたい:‘It has been suggested that heritage language
learnrs of other languages exibit characteristics similar to Japanese heritage learners (for example, for the
characteristics of Spanish heritage learners, see Valdes, 1995; Valdes and Geoffrion-Vinci, 1998: Ibid.).
Curricula for heritage learners should be designed with these characteristics kept in mind, and should
accomodate the different needs of individual learners’.そこで、新しいカリキュラムの開発が求められる時代がやってきたといえるだろう。
パソバ・オリガさんの学位論文についてのシリーズはとりあえず、今回で最後になります。パソバさんおよび林田先生のおっしゃっていることは、将来的には日本の公的教育機関が、日本や日本語の国家的・文化的尊厳を維持しつつ、かつ日本が多言語共生社会に変化しつつあることを踏まえ、日本語教育を変革させるべき、という主張です。私どもは、その変化の流れの中、ロシア語に軸足を置いたサービスを提供しています。
さらに私どもが属するкомпасというロシア語を継承語として扱い、日本語ロシア語のバイリンガルを対象にしたロシア語学校のグループがあります。現在8校ののロシア語学校がメンバーですが、一つ一つが保護者の希望やニーズに合わせた教育をしようと日々努力しています。受け入れ人数の制限はあるものの、保護者の選択肢はおそらく皆様の想像以上にあるはずです。Skypeによる遠隔授業に取り組んでいる学校もあります。何よりも、これらはいわゆる営利目的一辺倒の学校ではありませんので、まずはお子様の置かれた状況や今後の目標などを相談されることをお勧めいたします。ご一報いただければ、お宅に一番近いメンバーの連絡先をお伝えいたします。