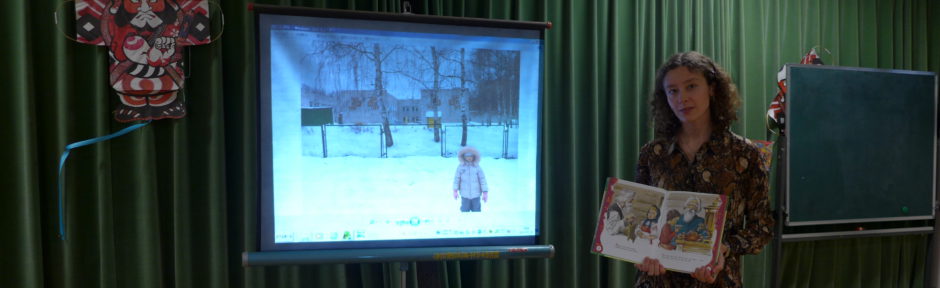前回に続いてパソバオリガさんの学位論文を参照します。以下青字部分は抜粋です。
日露結婚で生まれた子どもの多くが、アジア人ではないことが周囲に対しても格段に目立つ。Zimmerman (2010 :8 )は自身の捉え方(自己アイデンティティの形成)が、本人がいかに自分自身を捉えているかばかりでなく、他人の認識によっても成り立っていると語る。「人が自分を別のエスニシティに属するものと思いこもうとしても、外見(専門用語では表現型phenotype)という制約があることも認めなくてはならない」とするコーエン・ケネディ(2010:193)の指摘がある。
子どもの発達心理学においては、民族アイデンティ形成について研究が盛んであるが、子どもは大人になるまでに、民族アイデンンティティ形成期の三つの段階を通して成長しているとするラムゼー[Ramsey 2012]の指摘がある。
このような態度を取る子どもがいる。『息子のクラスには、「ハーフ」がいて、白人とのコミュニケーションを避け、日本人だけを友達に選んだ。自分がハーフであることに悩んでいた。』そのほか、「子どもは自己アイデンティティに迷っている。西洋人が彼らを仲間に入れてくれないし、アジア人も。。。自分の子どもからよく質問される:「お母さん、私たちは、何人?」それに対して「ハーフ」との返事に喜んでくれない。行動、考え方も違う。ヨーロッパ人とも、アジアン人とも。。。子どもからの正直な意見は、「ハーフ」ではなく、純日本人あるいは、純白人で踏襲生まれていたらよかったのに...」[Russian speaking community http://www.facebook.com 2013 年2 月16 日から]。
中島(2012)がまさしく示唆している通り、日本の学校に入ると、日本人ではないということでのマイナス・イメージがあり、アイデンティティが肯定されないケースもある。
そこでロシア語コミュニティでアイデンティティを肯定してあげるということも大事であると中島 (2012)がまとめている。
継承語を通じて自分の文化背景を認識するということに関しては、子どものアイデンティティ形成におけるポジティブな例があげられる:「私の家族のメンバー全員から(ロシア側の母親の家族)、子どもに対して『あなたは、ロシア人です』と言われ納得した。彼は満足しています。」[Russian speaking community http://www.facebook.com 2013 年2 月20 日]。こういったケースには、同化を促す傾向が強い日本学校文化の中を生きる子どもたちのアイデンティティ構築においては、ロシア語継承を通じて、自分がダブル・アイデンティティ保持者であるといったポジティブな進展が起きるのではないかと思われる。
このように、私どもの対象であるバイリンガルの生徒さんは日本人とロシア人あるいはロシア語を母語とする方とのカップルから生まれたお子さんのため、外見上アジア同士のカップルとは明らかに異なっている場合が多いです。さらに日露のバイリンガルのお子さんが日本の学校に入学する際の問題点として、同化を促す学校の意図と反して、友達同士の関係では、どうしても外国人ともみなされてしまう現実があり、このことが子供たちのアイデンティティの揺れの原因となると言う指摘です。ただし、ロシア語を継承語として習得する上で、ダブルアイデンティティと言う認識が構築され、これは本人にとってポジティブな認識であろう、とまとめられています。
私どもが指摘するまでも無く、ハーフのお子様の民族アイデンティティは本人にとっても家族にとっても大きな問題です。これを言わば攻撃的に解決するためには、やはり両方の民族の有する文化・言葉を習得しこれらに自信あるいは尊厳を持ち、それによってダブルアイデンティティを有することに肯定感が得られる、ようにしてあげることも一つの解決法でしょう。楽観的に見るならば、今後日本のみならずグローバルに国際結婚が増え、異なった人種間のハーフが増えていくことは自明ですので、そうした環境下での民族アイデンティティの研究は進むはずです。我々もこれらの研究を注視することを継続し、今後もこの課題に真摯に取り組み、ハーフの子供たちの将来をご家族と共に考えて行きたいと思います。