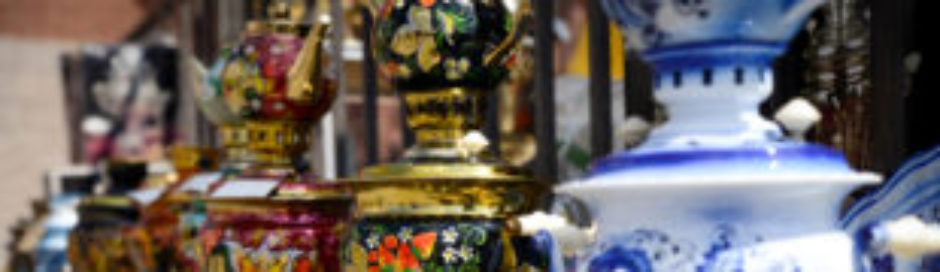前回はバイリンガルの分類について書きましたが、今回はJarucoのロシア語・日本語バイリンガルの育成方針に触れたいと思います。語学学習にあたっては、一般的に学習者の言語学習動機、「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」の4スキルのレベル、学習にあてられる時間などを十分に把握した後で学習計画を作成します。ただしバイリンガル教育を施すお子さんをお預かりする際には、「ご両親が考える理想のバイリンガルの姿」を伺うことが最も大切な質問になります。「ロシア語でも大学教育を受けられるバイリンガルに育てたい」というのが究極的な姿だと思いますし、Jarucoの設定している目標のレベルをそこにおいています。
その際、重要な事実としてお伝えすることは、「第二言語の習得において、聞く、話す、読む、書く、の4スキルは必ずしもバランスよく発達するものではない」ということです。 言語習得のメカニズムを考える場合、4スキル(話す、聞く、読む、書く)のうち、どれが最も重要かについて考えてみましょう。 人は、通常生まれた直後から満遍なくいくつかの言語に触れていれば、二つ以上の言語を母語として習得できる、ということがわかっています。これを「同時性バイリンガル」と呼んでいます。一方、母語の習得が確立されてから他の言語を習得することを「後続性バイリンガリル」と呼びます。幼児は、言語を流暢に話せるようになる1年くらい前までは聞くことによって言語を習得し、それに次いで、読むことや書くことができるようになります。耳からのインプット、つまり聞くことが言語習得、とりわけ母語確立の基礎なのです。
この点、親御さんは4スキルの内「話す」を偏重する傾向にあります。と言うのも、将来その言語を役立てようと思えば、その言語によるアウトプット、つまり「話す」、「書く」ができないと言語習得の意味が薄れてしまうという不安にかられるからです。 しかし子供たちは、聞くことにより、脳の中に言語構造を組み立てていっています。もし、子どもが目標言語であまり話さなくても、その言語について十分理解していれば、いわゆる「受容的バイリンガル」と分類できる状態にあり、その言語環境に一定期間(10日程度)置くことにより、流暢に話せるようになります。この様に、言語習得において、「話す」ことよりも、まず「聞く」力が最も必要なスキルと言うことができます。
もちろん、習得した言語を活用するには、その言語環境下での一定の対話の機会(意味交渉)が必要であることは間違いありません。研究によると、幼児の言語習得については、単にビデオを見せるだけでは効果がないということが分かっています。子どもは、言語とその意味を体験で理解するために、家族や友達のような意味交渉のできる対話者が必要です。外国語(目標言語)を遊びやその他の生活のために駆使する時間を計画的に設定し、実際の環境を模倣しての教育が不可欠です。
Jarucoのバイリンガル教育は、まずは「聞く」ことにより十分な情報をインプットし、ロシア語での生活体験、遊びの体験を計画的に配置して意味交渉を頻繁に行うことで、「話す」、「書く」のアウトプットを促し、ストレス無くロシア語が身につくよう設計されています。